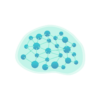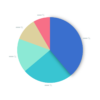生成AIと独立会計士
またしてもお久しぶりです。
細々とでも気が向いたときに更新していこうと思います。
気づいたら4月ですね、独立して4年目に突入しています(1月~)
最近思うこととして生成AIについて書こうと思います。
目次
気づけば“当たり前”になりつつあるAI
今更ですが、生成AIの進化がすごいスピードで進んでるのを本当に実感します。
ChatGPTやPerplexity、Claudeあたりはもう聞いたことある人も多いと思いますが、職種によっては「使えるかどうか」で仕事のスピードも成果もだいぶ違ってきてるような印象があります。
で、それを横目に見ていて「いや、これたぶん会計業界にも来るぞ…」って思ってる人、結構いると思うんです(特にXとかにいる人は)
でも、現場レベルで見れば「まだそんなに使われてないよね?」っていう空気もあって。
自分も最初は「会計士の仕事はさすがにすぐにはAIには無理だろう」と思ってました。ただ、最近はちょっとその考えが変わってきました。
意外と早く来るぞと。
実際、こんなふうに使ってます
自分自身が実際にAIを業務でどう使ってるか、ざっと挙げてみるとこんな感じです。
まだまだ使いこなせているかというと怪しいというかおいていかれている側になりかけている危機感があります。。
- 音声データからの議事録作成(文字起こしして要約)
- 制度改正の長文解説をざっくり要点整理
- 翻訳
- 知らない分野の初期調査(何から調べたらいいかわからんとき)
- ChatGPTに話しかけて論点整理(壁打ち的に)
- ググるよりもGeminiやChatGPTで概要つかむ(検索の時短)
とくに独立して一人で動いてると、こういうちょっとしたものでも助かりますね。
AIに聞くだけでは解決しないけど、知らないことを調査するとっかかりとか、そこまで深いこと知らなくてもいいがうわべだけ知っておきたいとかはまさにちょうどいい。
正直、会計士業界はまだ遠慮してる
ただ、業界全体としてはまだまだAI活用って控えめな印象があります。
理由はいろいろあるけど、ざっくり3つあると思ってます。
ひとつは、「自分の仕事にはまだ関係なさそう」って思ってる人が多いこと。
実際には関係あるのに、危機感があんまりまだないというか。他業種や同業でもめちゃくちゃ活用している人の変化見てると、「あ、これ思ったより早く来るな」って最近は感じる。
ふたつめは、AIが出してくる情報の正確性、信頼性の問題。
たしかに、会計基準とか会計の専門的な問いに関しては、今でもけっこう怪しい回答が返ってくることもある。仕訳作成なんかも、現状はまだまだですよね。
そして3つめ。これが一番大きいかもしれませんが、セキュリティの問題。
特に監査法人にいる人なんかは、機密情報を外部AIに入力するのはそもそもNGだったりするので、そもそも触れる機会が少ないというジレンマがあります。
でも、静かに迫ってきてる“変化の波”
とはいえ、AIの進化は止まりません。本当にものすごいスピードです。
ChatGPT、Gemini等でのDeep Researchの登場や他の生成AIも活用することで調査業務がめちゃくちゃ楽になったように、次は仕訳チェックとか、定型的なレビュー業務とかにも波が来るのは間違いないと思ってます。
一方で、これもめちゃくちゃ言われていることですが、AIがやってくれる作業が増えるってことは、逆に「人にしかできない判断」がもっと大事になってくるということでもあります。
たとえば、会計上の見積りとか、重要性の判断とか、クライアントと対話しながら詰めていく部分。そういう“会計の意思”に関わるところは、むしろこれから価値が上がるんじゃないかと思います。
監査法人にいる人、独立してる人、それぞれにチャンスとリスクがある
立場によってAIとの向き合い方もけっこう違ってきます。監査法人はもう離れているので想像ですが。
たとえば監査法人にいる人。たしかにセキュリティとかルールの問題で、自由にAIを使えない事情はあると思います。
でも、だからこそ外の世界に目を向けておかないと、「中にいて気づいたら時代遅れになってた…」なんてことになりかねない。
逆に、独立してる会計士は、動こうと思えばいつでも試せる環境にあるわけで。
だからこそ、「触れるか、触れないか」がチャンスにもなるしリスクにもなる。
特にスタートアップとかテック系のクライアントと関わってる人は、AI活用してるのが当たり前だったりするので、自分もキャッチアップしておかないと感覚がずれてしまうのはありそう。
最初から上手に使いこなす必要なんてないと思ってます。むしろ、「まず触ってみる」がすごく大事。どこまで使えるのか、どこからはやっぱり人が判断すべきなのか、実感しないとわからないことばかりです。
文章の下書きでも、制度調べでも、ちょっとでも役に立ったと思える経験が積み重なってくると、自分の中で「AIとの付き合い方」みたいなものが見えてきます。
最後に(危機感)
生成AIが会計士の業務をすべて代替するとは思っていません。
だけど思ったよりも多くの範囲をカバーしてきそうだし、それをうまく使えるかどうかでかなり差が開くんじゃないかと感じてます。
AIを“うまく使う人”と、“何もしてない人”。この差が、生産性だけじゃなくて、働き方とかクライアントへの提供価値にまで影響してくる時代は、意外とすぐそこまで来てるんじゃないかと。
今のうちに“使う側”に立っておく。その準備として、まずはちょっとずつでも触れてみる。そんな一歩が、数年後の自分の働き方を大きく変えているかもしれません。
PS
あまり税務やってないので何ともですが、税理士業界の方が生成AIの影響受けそうだよね。
しかもあまりその辺キャッチアップできる人多くなさそう(もちろんいっぱいいると思うけど比率として)
周りの年齢高めの税理士と会話してると驚くほど感覚が。。。